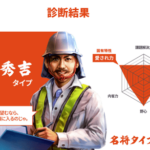生産性と社員のモチベーションが
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
「知識」は貯めるだけでは意味がない。スマホ時代に考える“使う体験”の価値
朝のTikTokで気づいた、脳とスマホの関係
今朝、TikTokをぼーっと眺めていたら、ある脳科学者の方がこんな話をしていました。
「スマホを使いすぎると、健康な人でも発達障害(ADHD)に似た状態になる可能性がある」
ドキッとしました。スマホ依存がどうとか、集中力が落ちるとか、よく耳にする話ではあるけれど、「発達障害に似た状態になる」というのは、ちょっとレベルが違う話に感じます。確かに、通知が鳴ればすぐに反応し、次々と情報に飛びついて、気づけば何をしてたのか分からない——そんなこと、僕にも日常茶飯事であります。
「知識」は使ってこそ、脳に定着する
これを聞いて思い出したのが、よく話題になる「東大生のノートの取り方」。特に注目されているのが「コーネル式ノート」なんですが、あれのキモは「インプットしながら考える、つまり同時にアウトプットすること」にあるんですよね。

ただ書き写すんじゃなくて、学んだことを自分の言葉で整理し、要点をまとめて、すぐに使ってみる。そうすることで、情報は「自分のもの」になる。
これは実際、僕自身も強く感じています。
スマホやパソコンに何でもメモしておける今、便利なんだけど……気づいたら「自分の頭で考えなくてもいい状態」になっている。そして、いざという時に「あれ?思い出せない……」ってなる。あれは、自分の脳みそに情報が残っていない証拠なんですよね。
子どもには特に、「頭を使う練習」が必要だと思う
発達段階にある子どもたちには、特にこの問題は深刻です。
まだ脳のネットワークが形成途中の時期に、受け身な情報摂取ばかりしていたら、「考える力」が育たないまま大人になってしまうかもしれない。
だから、やっぱりスマホの使用にはある程度の制限が必要だと改めて思いました。もちろん便利さはあるけれど、「すぐに調べる」「すぐに答えがわかる」環境ばかりでは、自分の頭で考える機会が奪われる。
実際、僕ら大人だって、「あれ?あの人の名前なんだっけ?」「あの店、どこにあったっけ?」って、スマホがなかったら全然思い出せないことって増えてるじゃないですか。それってつまり、“考える”という行為を外部に委ねすぎてるってことだと思うんです。
教育現場や人材育成にも通じる大事な視点
これは、子どもだけの話じゃありません。僕が普段取り組んでいる人材育成や組織デザインの分野でも、まったく同じことが言えます。
どれだけ知識を詰め込んでも、それを「使う体験」をしないと意味がない。TOC(制約理論)やMG(マネジメントゲーム)もそう。座学で学ぶだけじゃなくて、実際に体験する中で、初めて「腑に落ちる」んです。
知識は血肉にして初めて武器になる。だから、学び方を変えないと、働き方も変わらない。
まとめ
情報があふれる今の時代、「どれだけ知っているか」よりも「どう使えるか」が問われています。スマホが便利すぎる今だからこそ、自分の頭で考える時間をあえてつくる。アウトプットを前提としたインプットに切り替える。これは大人も子どもも同じ、大事な習慣です。
僕たちの職場でも、研修では「覚える」ことより「やってみる」「話してみる」「失敗してみる」ことを大事にしています。人は、体験を通じてしか変わらない。
だからこそ、情報を“貯める”のではなく、“使う”ことを意識してみてください。
もっと知りたい方へ
人材育成や組織デザイン、TOCやMGの体験型研修にご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。実際に「使ってみる」ことで、驚くほどの変化が起きます!
お問い合わせ

| 中小製造業専門のIT参謀 村上 郁 (むらかみ かおる) |
|
| 支援内容 |
ランディングページの制作支援 ITシステムの構築・運用のサポート |
|---|---|
| 活動拠点 | 奈良県生駒市 |
| 営業時間 | 平日9時~18時 |
| 定休日 | 土日祝 |
関連記事
カテゴリー
- 1on1 (1)
- AI (3)
- BBAサミット (5)
- DXって何だろう (71)
- IoT (1)
- IT化で作業効率を上げる (28)
- MG(マネジメントゲーム) (12)
- NJE理論ブログ (27)
- SNS (13)
- Tips (1)
- TOC(制約理論) (19)
- おうち時間の過ごし方 (21)
- オンライン授業のすすめ (8)
- お客様づくり (7)
- お知らせ (5)
- ほめ育 (35)
- インフラ整備 (10)
- オススメ記事 (681)
- オンライン (10)
- セキュリティ (11)
- ダメなシステムの使い方 (9)
- デジタルで何が変わる? (44)
- パラレルワークで分かった事 (7)
- ブログ (10)
- 中小企業のシステム構築のポイント (49)
- 中小企業のホームページ (33)
- 令和時代の人材育成 (89)
- 伝わってますか?その情報発信 (120)
- 展示会 (6)
- 心理的安全性 (26)
- 思索ノート (1)
- 情報収集 (8)
- 指示ゼロ経営 (5)
- 採用 (7)
- 時間の使い方 (8)
- 楽しいIT活用術 (11)
- 独立、自営の道 (14)
- 生産性アップのためのネット活用 (9)
- 間違いだらけのネットの使い方 (4)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
タグ
月別記事
- 2026年2月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (13)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (6)
- 2025年1月 (10)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (5)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (4)
- 2023年9月 (14)
- 2023年8月 (10)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (8)
- 2023年4月 (13)
- 2023年3月 (9)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (7)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (31)
- 2021年7月 (30)
- 2021年6月 (30)
- 2021年5月 (31)
- 2021年4月 (30)
- 2021年3月 (31)
- 2021年2月 (28)
- 2021年1月 (31)
- 2020年12月 (31)
- 2020年11月 (30)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (30)
- 2020年8月 (31)
- 2020年7月 (31)
- 2020年6月 (30)
- 2020年5月 (31)
- 2020年4月 (14)
- 2020年2月 (13)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)