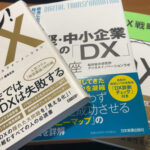生産性と社員のモチベーションが
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
【番外編】「昔はこうだった」は通用しない――科学が否定した昭和的教育と現場の未来
「自分たちは怒られて育った。だから今の若い子にも厳しく接するべきだ」
中小企業の現場やベテラン経営者の口から、今もたびたび聞こえてくる言葉です。
その背景には、過去の成功体験と、責任感からくる「育てなければ」という想いがあるのでしょう。
しかし今、この昭和的な教育観は、科学的にも倫理的にも明確に否定されています。
なぜなら、怒りや体罰、恐怖に基づく教育は、人を育てるどころか、萎縮させ、成長を止めてしまうからです。
🔬 科学が示した“怒鳴る教育”の限界
| 分野 | 科学的結論 | 解説(日本語訳) |
|---|---|---|
| 教育心理学 | 攻撃性が増し、学習効果は低下する | 叱責や体罰は「恐怖で従う」行動を一時的に生むが、長期的には反発や無気力を育む(アメリカ心理学会 2019) |
| 脳科学 | 脳の成長に悪影響を及ぼす | 幼少期から怒鳴られ続けた子の脳は、恐怖に過敏に反応するようになり、判断力や感情制御力が低下する(ハーバード大研究 2011) |
| 行動科学 | 正の強化(褒める)の方が持続性が高い | スキナーの実験でも「罰よりも報酬のほうが行動は続く」と結論づけられている(1953年) |
📊 図解案:教育アプローチ別 成果の比較(参考)
| 教育方法 | 短期効果 | 長期効果 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 怒鳴る・叱る | △ 行動抑制 | × 無気力・反発 | 負のスパイラル |
| 放任・無関心 | × 放置される | × 成長せず離職 | 無責任な放置 |
| 共感×期待(心理的安全性) | ○ 話し合い | ◎ 自律と定着 | 最も成長につながる |
🧩 昭和の教育を否定するのではなく、「進化させる」
ここで重要なのは、昭和の教育を一括りに否定することではありません。
「礼儀」「継続」「責任感」など、当時大切にされていた価値観には、今も学ぶべき点があります。
しかし、それを**「恐怖と怒り」で伝えるやり方」では、もはや通用しない**のです。
「自分たちが受けた教育は、本当に“人を育てていた”のか?」
この問いに、経営者自身やベテラン自身が向き合うことが、次の世代に道をつなぐスタートラインになります。
🔁 若手が育つ会社へ――変化する“育て方”
-
怒鳴る代わりに「伝える力」を磨く
-
経験を背中で見せるだけでなく「仕組み」として残す
-
「やって見せて、やらせてみて、ほめて認める」文化へ
これこそが、令和の現場で機能する育成の在り方です。
お問い合わせ

| 中小製造業専門のIT参謀 村上 郁 (むらかみ かおる) |
|
| 支援内容 |
ランディングページの制作支援 ITシステムの構築・運用のサポート |
|---|---|
| 活動拠点 | 奈良県生駒市 |
| 営業時間 | 平日9時~18時 |
| 定休日 | 土日祝 |
関連記事
カテゴリー
- 1on1 (1)
- AI (3)
- BBAサミット (5)
- DXって何だろう (71)
- IoT (1)
- IT化で作業効率を上げる (28)
- MG(マネジメントゲーム) (12)
- NJE理論ブログ (27)
- SNS (13)
- Tips (1)
- TOC(制約理論) (19)
- おうち時間の過ごし方 (21)
- オンライン授業のすすめ (8)
- お客様づくり (7)
- お知らせ (5)
- ほめ育 (35)
- インフラ整備 (10)
- オススメ記事 (680)
- オンライン (10)
- セキュリティ (11)
- ダメなシステムの使い方 (9)
- デジタルで何が変わる? (44)
- パラレルワークで分かった事 (7)
- ブログ (10)
- 中小企業のシステム構築のポイント (49)
- 中小企業のホームページ (33)
- 令和時代の人材育成 (89)
- 伝わってますか?その情報発信 (120)
- 展示会 (6)
- 心理的安全性 (26)
- 思索ノート (1)
- 情報収集 (8)
- 指示ゼロ経営 (5)
- 採用 (7)
- 時間の使い方 (8)
- 楽しいIT活用術 (11)
- 独立、自営の道 (14)
- 生産性アップのためのネット活用 (9)
- 間違いだらけのネットの使い方 (4)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
タグ
AI
Chatwork
DX
Googleカレンダー
IT参謀
MOBIO
NJE理論ブログ
Slackマナー
Twitter
YouTube
ZOOM
「A4」1枚アンケート
おうち環境整備
ほめ育
ものづくり企業
オンライン展示会
オンライン授業
コミュニケーション
コロナ禍
デジタルデトックス
デジタルトランスフォーメーション
デジタル化
デジ活
ドラゴン桜
ドラッカー
パラレルワーク
ペライチ
ライブ配信
ランディングページ
中小製造業のDX
人材育成
価値観
半沢直樹
大阪勧業展2020
情報発信
新卒採用
新型コロナウイルス
時間の使い方
毎日ブログ
生産性
異端児エリート養成大学校
社長のデジ活
緊急事態宣言
顧客目線
麒麟がくる
月別記事
- 2025年11月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (13)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (6)
- 2025年1月 (10)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (5)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (4)
- 2023年9月 (14)
- 2023年8月 (10)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (8)
- 2023年4月 (13)
- 2023年3月 (9)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (7)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (31)
- 2021年7月 (30)
- 2021年6月 (30)
- 2021年5月 (31)
- 2021年4月 (30)
- 2021年3月 (31)
- 2021年2月 (28)
- 2021年1月 (31)
- 2020年12月 (31)
- 2020年11月 (30)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (30)
- 2020年8月 (31)
- 2020年7月 (31)
- 2020年6月 (30)
- 2020年5月 (31)
- 2020年4月 (14)
- 2020年2月 (13)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)