

生産性と社員のモチベーションが
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
「人はもともと善良である」から始める経営—人のせいにしない仕組みづくりの本質
毎週月曜に開催される「月曜たくらみ会」。
今回は前回からの続きとして星野玄さんの発表にあった「人のせいにしない仕組みづくり」について深める対話をしました。

(私はこの問いに「うん、確かにうちの会社はそれだけじゃ無理だな」と頭がもげそうなほど頷く)
「人のせいにしない」と「仕組みづくり」の間に、重要な要素があるのではないか?
例えば、メンタルや感情が関係しているのでは? という問いかけからスタート。
対話の中で最初に私に刺さったのは、「仕組み化」の技術を支えるベースにあるのは「対話」であり、その対話を成立させるには「心理的安全性」が必要不可欠だということ。
確かに、TOC(制約理論)やMG(マネジメントゲーム)に集まってくる人たちは、高い視座を持っている傾向が強い。
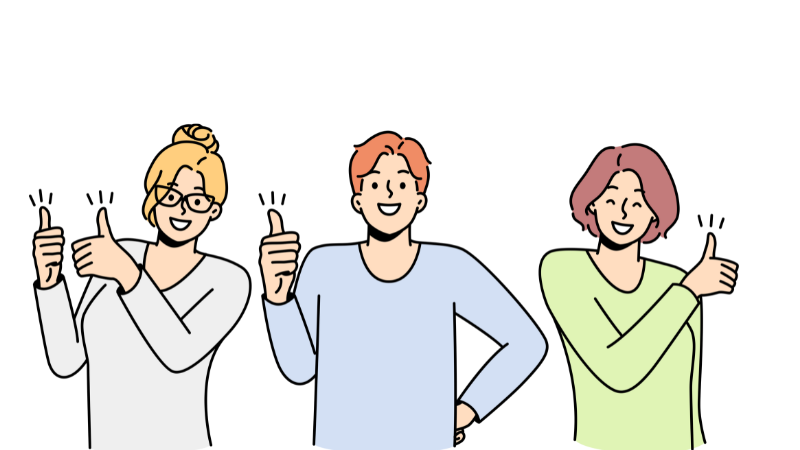
では、うちの会社の人たちはどうか? もしかすると「視座が低い人の集まり」なのか?と考えると、そこには違和感を覚えます。
「もともと善良」とは?
この対話の中で、私は「人はもともと善良」とは思えない場面があることを話しました。確かに、人は「正義」や「善良」という言葉を使いますが、傍から見ると実際にはそうとは思えない状況を何度も見てきたからです。
しかし、その時に玄さんが言った言葉にハッとさせられました。

私はいつの間にか「善良かどうか」を判断しようとしていました。でも、その判断はあくまで自分の基準です。
仕組みを作る上では、まず「人はもともと善良である」という前提をそのまま置くことが必要なのではないか?と気付かされました。

環境が人をつくる
さらに、この考えがすっと腑に落ちたのは、かずみんさんの話を聞いたときでした。
彼女の前職では、やくざの人が顧客として訪れることがあったそうです。最初は怖いと感じたものの、その人の生い立ちを知ると、「私も同じ境遇ならグレたのではないか」「人は環境によって変わる」と思ったと言います。
そう、人のせいにしないとは、「人が生まれながらに邪悪なのではなく、環境が影響を与えている」ということとつながります。
「他人のせいにしない」ではなく「人のせいにしない」というのはそういうこと。だからこそ、「人のせいにしない仕組みづくり」には、環境整備が重要なのです。
仕組みづくりの本質とは?
この対話を通じて、「人のせいにしない仕組みづくり」には、以下のようなポイントがあると感じました。
「人はもともと善良である」ことを大前提とする
(人の善悪を判断しない)
心理的安全性を確保する
(安心して対話ができる環境をつくる)
対話をする中で仕組みを作っていく
(善良即ち仕組みができる、わけではない)
TOCでは「ボトルネックの解消」が鍵になりますが、それは技術的な仕組みだけでなく、組織の「心のボトルネック」を見つめ直すことでもあります。
結論:「人はもともと善良である」から仕組みをつくる
今回の対話を通じて、「人のせいにしない仕組みづくり」は、単なる技術論ではなく、「人はもともと善良である」という大前提から環境を整備することが大切だと改めて感じました。
人は「正しいか」「間違っているか」ではなく、どのような環境で育ち、どのような影響を受けたかによって変わります。
だからこそ、人のせいにしない仕組みづくりには、対話のできる環境整備が不可欠。
まずは「人はもともと善良である」と腑に落とすところから仕組みづくりを考えてみませんか?
さぁ、『ザ・チョイス』を読み直そう
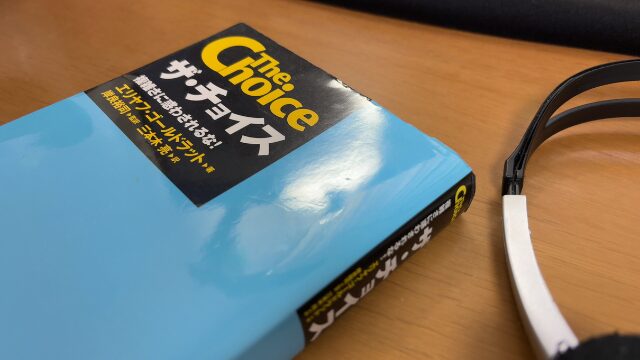
お問い合わせ

| 中小製造業専門のIT参謀 村上 郁 (むらかみ かおる) |
|
| 支援内容 |
ランディングページの制作支援 ITシステムの構築・運用のサポート |
|---|---|
| 活動拠点 | 奈良県生駒市 |
| 営業時間 | 平日9時~18時 |
| 定休日 | 土日祝 |
関連記事
カテゴリー
- 1on1 (1)
- AI (3)
- BBAサミット (5)
- DXって何だろう (71)
- IoT (1)
- IT化で作業効率を上げる (28)
- MG(マネジメントゲーム) (12)
- NJE理論ブログ (27)
- SNS (13)
- Tips (1)
- TOC(制約理論) (19)
- おうち時間の過ごし方 (21)
- オンライン授業のすすめ (8)
- お客様づくり (7)
- お知らせ (5)
- ほめ育 (35)
- インフラ整備 (10)
- オススメ記事 (681)
- オンライン (10)
- セキュリティ (11)
- ダメなシステムの使い方 (9)
- デジタルで何が変わる? (44)
- パラレルワークで分かった事 (7)
- ブログ (10)
- 中小企業のシステム構築のポイント (49)
- 中小企業のホームページ (33)
- 令和時代の人材育成 (89)
- 伝わってますか?その情報発信 (120)
- 展示会 (6)
- 心理的安全性 (26)
- 思索ノート (1)
- 情報収集 (8)
- 指示ゼロ経営 (5)
- 採用 (7)
- 時間の使い方 (8)
- 楽しいIT活用術 (11)
- 独立、自営の道 (14)
- 生産性アップのためのネット活用 (9)
- 間違いだらけのネットの使い方 (4)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
タグ
月別記事
- 2026年2月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (13)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (6)
- 2025年1月 (10)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (5)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (4)
- 2023年9月 (14)
- 2023年8月 (10)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (8)
- 2023年4月 (13)
- 2023年3月 (9)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (7)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (31)
- 2021年7月 (30)
- 2021年6月 (30)
- 2021年5月 (31)
- 2021年4月 (30)
- 2021年3月 (31)
- 2021年2月 (28)
- 2021年1月 (31)
- 2020年12月 (31)
- 2020年11月 (30)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (30)
- 2020年8月 (31)
- 2020年7月 (31)
- 2020年6月 (30)
- 2020年5月 (31)
- 2020年4月 (14)
- 2020年2月 (13)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (1)
















